円東寺を地域の
サードプレイスに

円東寺をどんなお寺にしたいと考えていらっしゃいますか。
人々の”第三の場所”にしたいと思っています。ペットを飼うと和むのと同じで、地域にワンクッションあると殺伐とした空気が少し変わる、お寺をそんな存在にしたいですね。ここ流山の昔ながらのまちの人と開発で来た人との交流が少ないので、その方々の交流・交差点となって結節点になったらいいと思っています。
そういう意味では、地域にいる人々がみんな知り合いになればいいと思っています。喧嘩が起きるのもお互いに知らない人だからです。足を踏んだとか、肘が当たったとかは友人同士の間では喧嘩にはならないですよね。
お墓は家単位、親戚単位ですが、永代供養墓(合同墓)は知らない人の集まりです。仲良くなれとは言いませんが、皆が知り合いになれば喧嘩は起こらないと思っています。
お寺というのは、例えば隣の家の敷地まで雪かきをしても許されるのがお寺です。だからこそみんなを繋げることができるのかなと思います。
お寺の中に庭を作る
アンカレッジとの出会いのきっかけをお教えください。
きっかけは、宿坊研究会の堀内さん(アンカレッジの顧問)とのご縁でした。実は以前、堀内さんが円東寺の写経会に参加されたことがあり、また、私は宿坊研究会主催の新年会にも参加していたため、堀内さんのことは以前から知っていました。その堀内さんから声をかけられ、アンカレッジが主催する樹木葬の勉強会に参加したのが、最初でした。
その後、現在の場所に第1期をつくり、おかげさまで好評をいただきました。2期の整備へとつながっています。もともと、永代供養墓や樹木葬の仕組み自体は知っていて、「これは良いものだな」とは思っていました。
実際にアンカレッジの樹木葬をご覧になって、率直にどのような印象をお持ちになりましたか。
「樹木葬」とひとことで言っても、事業者によって形やデザインは本当にさまざまです。「お墓=石」という考えからなかなか離れられないのが現実です。木や草花よりも石のほうが長く形に残りますから。
そのなかで、アンカレッジの樹木葬は「石と緑のちょうど良いバランス」が取れていると感じましたね。
”一本足打法は危ない”
ということ

アンカレッジと協業してできるようになったことをお聞かせいただけますか。
寺の経営を安定させるために、樹木葬は必要な取り組みだったと思います。
先ほどもお話ししましたが、元々無住のお寺だったので、このお寺を支えているのはお檀家様です。お檀家様の多寡にかかわらず本堂などの施設を維持していくことの経済的負担は一緒です。樹木葬の導入前はこのままでは護持費をあげざるを得ないのでないかといった状況でしたが、結果として、護持費は据え置くことができました。
私が住職になった当初は、何年もお給料をもらえない状態が続きました。寺としての資産もなかったので、寺とは別に師匠のところに勤めて生計を立てていたんです。今では少しずつ資産もでき、寺からの収入も得られるようになりましたが、これは堀内さんが言うように「一本足打法は危ない」ということを強く実感しています。
多くの寺院は、葬儀や法事のお布施に収入を依存しています。けれども、それだけでは未来に対してあまりに不安定。何か新しいことを始めようとする住職はまだ少ないのが現実です。後継者に安心してバトンを渡すためにも「今が良いからこそ、備えておくべきだ」と私は思います。

アンカレッジスタッフと実際に仕事をされてみて、どのような印象をお持ちになりましたか?
アンカレッジのスタッフの皆さんには本当に感謝しています。掃除やスケジュールの管理など、私の不得意な部分を支えてもらっています。
私はなるべくお金に関わらないようにしています。お布施の袋の中身も見ずに家内に渡しています。中身を見てしまうと、知らず知らずのうちに接し方が変わってしまう気がして。それが嫌なんです。だから営業や契約など、お金に関わる部分はプロに任せた方がいいと思っています。
アンカレッジの素晴らしいところは、スタッフのご家族が契約してくださっていること。これは本当にすごいことですよ。自分たちが誇りを持って関わっている証拠です。
アンカレッジの提案する
”価値”
樹木葬を選ばれた信徒様と接する中で、何か新たな発見や、お気づきになった点はございますか?
様々なご供養の選択肢がある中で、あえて樹木葬(永代供養墓)を選んだ方々なので、入り口は宗旨宗派不問ではあるけれども、むしろなんとかして供養したいという気持ちは強いなと感じます。
仏教の教義云々ではなく、故人を供養したいという想いが感じられます。供養を求めているので、仏教の教えが乾いた土に水をあげればスーと染み込んでいくように伝わると思います。その点では檀家様と特段違いや違和感がなく信徒様とコミュニケーションが取れています。また、そもそもお寺がやっているということがわかっている方がほとんどなのかなとも感じますね。仏教、お寺が嫌いな人はまず来ないです。ですので宗旨宗派不問でも問題はありません。

本日は貴重なお話をありがとうございました。最後に、もし樹木葬を始める前のご自身に何かメッセージを送るとしたら、今、何と伝えたいですか?
心配しなくても大丈夫と言うことですね。“お金を稼ぐ”ことではなく、“境内を整える”ことなんです。これから何十年、あるいはそれ以上先の未来を見据えたときに、いろいろな選択肢があるというのは大事なことだと思います。様々なご事情を持つ方々がお見えになることを想定したとき、代々墓だけでなく、樹木葬や永代供養墓(合同墓)など、幅広い形を用意した方がよいと考えています。そして、自分がいなくても布教ができる仕組みも大事だと感じています。たとえば、絵心経のマニ車。あれを見て、「この絵、なんだろう?」と興味を持った方が、自然と仏教やお経に関心を持ってくれる。こちらから無理に説明をしなくても、仏教との接点が生まれる仕掛けになっています。
そういった意味でも、アンカレッジが提案するものは「お墓」という枠を超えて、お寺にもお墓を求める人にも価値ある“仕組み”になっていると思います。





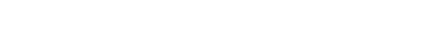
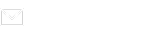
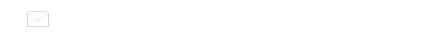

ご住職の自己紹介をお願いいたします。
埼玉県の大宮でサラリーマンの家庭で育ち、叔父が流山で住職をしていたので幼い頃からお寺には出入りをしていました。昔、叔父から「僧侶にならないか」と誘われたこともありましたが、その時は僧侶・住職になるつもりはありませんでした。その後、大学に進学し周りが就職活動を始めた時に、満員電車が苦手だったりで「自分はサラリーマンに向いていないな」と感じました。とにかく家でできる仕事が良いと考えていた時に、改めて叔父より僧侶にならないかと誘われて今に至ります。実は、その頃脚本家になりたかったというのもあり、僧侶(住職)なら物書きもできるかも、という想いも後押しになりましたね。当時、お坊さんはもっと浮世離れした仕事だと思っていましたが、実際には違いましたね(笑)お坊さんは一人で完結できる仕事で、私にとっては天職だと思っています。